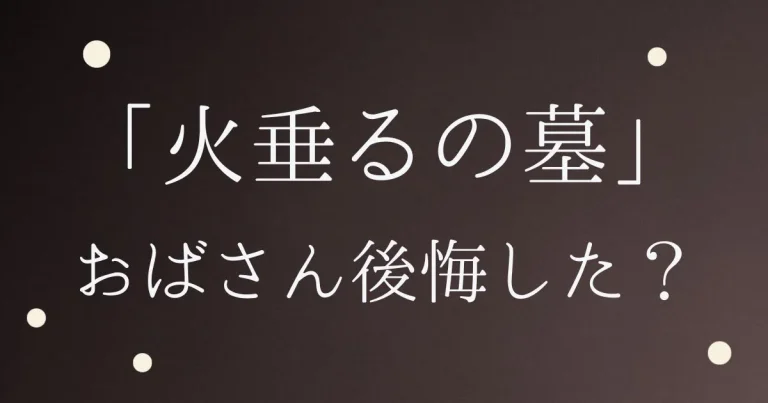ジブリ映画『火垂るの墓』の中でも、西宮のおばさんの行動やセリフは視聴者の心に強く残ります。
戦争下の極限状況で、清太と節子を引き取ったおばさんは本当に冷たい人だったのか――?
本記事では、『火垂るの墓』のおばさんは後悔していたのか、正論なのかを、セリフや行動、背景からおばさん目線と清太目線で考察します。
※この記事にはネタバレが含まれます。
おばさんは何者?人物像と立場【火垂るの墓】

まずは、西宮のおばさんがどんな人物で、どんな状況に置かれていたのかを整理します。
清太・節子との関係性
おばさんは、「清太の父の従弟の嫁」です。
ふたりとは血が繋がっておらず、遠い親戚(4親等の傍系関係族)だということになります。
おばさんの戦時中の生活環境
おばさんの登場時の家族構成は「本人、娘、下宿人」の3人で暮らしています。
西野宮市に住んでいます。
おばさんの旦那について、作中では言及されていませんが、原作小説によれば死亡している可能性が高い(未亡人)とされています。
また、作中の冒頭で、清太が梅干しや干し芋など豊富な食糧を帰ってきたときの、
「非常時いうても、あるところにはあるもんだね」
引用元:映画『火垂るの墓』
というおばさんのセリフから、経済的に豊かではなかったことが伺えます。
おばさんが清太と節子を引き取った理由
おばさんが清太たち2人を引き取った理由については、「焼け出されたら置いてもらうことになっていた」からです。
この事実は、作中で清太の口から語られています。
おばさんは後悔していたのか?本編から探る【火垂るの墓 考察】

おばさんの後悔を感じさせる表情・場面
作中で、おばさんの後悔を感じさせる表情や場面をあるとすれば、「清太と節子が、おばさん家を出ていったとき」です。
おばさんは、「どこ行くの?」と行先を尋ねました。
離れていくふたりの笑い声が聞こえるとハタと立ち止まり、彼らの後ろ姿を見て眉をしかめます。
演出の意図と監督のメッセージ
高畑勲監督は、おばさんについて、
“今は善人かもしれないけど、常に西宮のおばさんのようになってしまう危険性が孕んでいることに怯えてほしい”
という内容をインタビューで答えています。
つまり、おばさんは善人ではなく冷たい人物像として描かれていることになります。
また、映画『火垂るの墓』は、“清太が社会的に孤立していくことで悲惨な最期を迎える物語”なのだといいます。
筆者の考察|おばさんは後悔していたのか?
これらのことを踏まえると、おばさんが心から後悔している可能性は低いように思えます。
もし後悔していたとしても、ふと思い出してはすぐ忘れる程度のものだったのではないでしょうか。
なぜなら、おばさん目線で寄り添う心があれば、映画の社会的孤立という1つのテーマは薄まってしまうからです。
さらに、本当に後悔していたとすれば、1度くらい横穴を覗きにきているはずだと思えるからです。
農家のおじさんが「よく謝ってあそこに置いてもらいなさい」と清太に伝えていますが、それはおばさんから愚痴のようなものを聞かされていた、または噂で耳にしていた証拠。
清太が駅構内でホームレスになっているラストからも、おばさんの関心は薄めだったと思えます。

おばさんから清太に向けられた「疫病神」などという文句は、日頃の鬱憤がたまった結晶ですから、
実際のところは「厄介払いできた」「いっぱいお世話してあげた」「他に親戚がいるならいいか」という感情が強かったのではないでしょうか。
もしかすれば、おばさんが生きている間に生活が豊かになれば、ふと思い出して「悪いのはあの子たちではなく、戦争だった…」と幼い兄妹とケンカしたことを後悔する日がくるのかもしれません。
関連記事:火垂るの墓│伝えたいことは?実話や「ジブリじゃない」と言われる理由
おばさんは正論?セリフから読み解くそれぞれの目線・心理【火垂るの墓 考察】
おばさんは、視聴者目線からすると「ひどい、冷たい、嫌い!」などと思わせる言動が多いです。
なぜ清太に厳しかったのか?
清太とおばさんのやりとりの背景には、衝撃的な事実が隠されています。
ここでは、印象的な場面やセリフをあげ、それぞれの目線で心理を紐解きます。
おばさん目線―清太のひどさ
清太の両親についてのやり取り
幾つかのセリフから、おばさんは、最初から、清太たちを長く引き取っておくつもりはなかったことを予感させます。
たとえば、「母親のお見舞いに行って、この先のことを話し合わないと…」
と言っているし、
「お父さんに連絡した?」と何回か気にかけています。「東京に親戚いるでしょう」とも。
このことから、あくまで一旦互いの家に避難しましょう、という約束であり、その後もずっと面倒をみる予定はなかったと思われます。
清太から母親の死を聞いたあとの落胆のリアクションは、「これからどうしよう…」と思い詰めている風にも見えます。
おばさんからすれば、梅干しやお米などの食糧は、清太と節子の預かり代として、受け取って当然だったのかもしれませんね。
ご飯のシーン

母親の着物を売ったあと、3人(おばさん、清太、節子)でご飯を食べているシーンです。
節子:「雑炊イヤや」
~中略~
清太:「見てみ。昼はお米やから、雑炊、我慢して食べ」
おばさん:「ええかげんにしとき!家におるもんは、昼かて雑炊や。お国のために働いている人らの弁当と、一日中ぶらぶらしているあんたらと、なんで同じや思うの。
清太さんな、あんたもう大きいねんから、助けあいいうこと考えてくれな。あんたらはお米ちっとも出さんと、それでご飯食べたいっていうても、それはいけませんよ。通りません!」
引用元:ジブリ映画『火垂るの墓』
このセリフのやり取りから分かることは、この食事シーンは、清太の母親の着物を売って分けたお米のうち、西宮の家にとったお米からふたりに提供していたということです。
当然、普段も、みなしごふたりが持ってきた食材のみで作っているわけではありません。
西宮の家の在庫や、部屋を提供しているのです(下宿人をとればお金が稼げる)。
なのに感謝の気持ちどころか「雑炊やだ」「雑炊我慢して食べなさい」という兄妹のやり取りが目の前で繰り広げられるのは、ストレスになりますね(笑)。
さらに、文句を言われたため「食事は別々!」としたとたん、清太は貯金を下ろしてきてふたりのために七輪を買ってきます。
これに対し、おばさんは「ごめんもない」「当てつけだ」と憤慨しています。
“だったら、横穴に住めばいいのに”という文句が出てしまうのも理解できます。
これらのことから、
おばさん目線では、清太には、助け合いの精神がなく、国のためになにもしない。感謝もごめんなさいもなく家計を圧迫する、ストレスの貯まる存在だったといえるでしょう。
正論かどうかでいうと、一理あるといるでしょう。
清太目線―おばさんの冷たさ
続いて、清太目線のおばさんはどんな人でしょうか?
母親の死について

おばさんが、清太の母親の着物を売ることを提案し、節子が泣いて抵抗するシーンです。
節子が母親の着物に執着をみせています。おそらくこの頃には既に、節子はおばさんから“母親が亡くなったこと”を聞かされていた可能性が高いです。
節子:「お母ちゃんもお墓に入ってんねんやろ? うち、おばちゃんに聞いてん」
引用元:ジブリ映画『火垂るの墓』
節子が真実を知っていたことを知り、清太はたまらず涙します。
実は清太は、母親の死について、以前にこのようにおばさんに告げているのです。
おばさん:「なんやて、死にはったん。そんならそうとなんですぐにいうてくれはれかったん。水臭い子やなぁ」
清太:「節子に知られとうなかったんです」
引用元:ジブリ映画『火垂るの墓』
清太は、母親の遺骨を傍に置きたかっただろうに、節子を悲しませないように、家の庭の植木のなかに隠していました。
おばさんに、兄としての決意を台無しにされる結果となりました。
梅干しのシーン
あんなにあった梅干しが、いつのまに無い?…というシーンです。
清太:「僕が持ってきた梅干し、もうないんですか?」
おばさん:「そんなもん、とうにのうなったやないの」
~中略~
節子:「そやかて、あれうちのお米やのに」
引用元:ジブリ映画『火垂るの墓』
このセリフのやりとりと同時に、おばさんはおにぎり(娘たちのお弁当)を結んでいます。このことから、暗に“梅干しの行方”のメッセージが含まれていると思われます。
つまり、清太の梅干しは、おむすびの具として消費されていた可能性が高いのです。
もし梅干しが食卓に出されていなければ、清太と節子はほとんど食べられていなかったということになります。
さらに、我が物顔で母親の着物を売ったあとの「嫌なら出て行きなさい!」はストレスがたまりますね(笑)。
“おばさんの元に帰りたくない”という清太の決断も頷けます。
娘も冷たかった?
おばさんの娘も、一件優しい性格に思えますが、肝心なところでは他人事だったようです。
僅か4歳の節子の雑炊がほとんど汁なことに気づいても、顔を染めるだけで、母親に物申したり、分けてくれたりすることはしませんでした。
清太と節子がおばさん家から去るとき、笑い声と共に去っていく様子は未練ゼロ。娘や下宿人との別れの挨拶は必要ありませんでした。
このことからも、あの家の住人たちから愛情を感じられていなかったのだと思えます。
清太目線では「自分たちには汁ばかり」「自分たちのお米や梅干しなのに、に叱られる」と理不尽な扱いに滅入っているけれど、肩身が狭くてハッキリ文句もいえない怖い存在。居心地の悪い家でした。
ひもじくても、ふたりで横穴で暮らしているほうが気が楽だし笑顔になれました。
ただ、死後に最後らへんの人生を振り返っている清太は辛そうに見えます。節子が亡くなったのだから当然ですね。
きっと、後悔しているのは清太のほうなのでしょう。
関連記事:火垂るの墓│伝えたいことは?実話や「ジブリじゃない」と言われる理由
おばさんは本当に冷たくてひどいのか?【火垂るの墓 考察】
おばさんは元々は冷たい人ではないと思います。
もしおばさんがひどいと非難されるべきならば、当時の人々の多くを非難せねばならなくなるでしょう。
なぜなら、戦争の末、為すすべなく乞食となってしまったに青年(清太)相手に「日本の恥」という心ない言葉がかけられる時代なのです。人々の心の余裕なさが伺えます。
現代で例えるなら、被災が起こったとき、先の見えない食糧難のなか、自分が蓄えていた食糧を、自分らの家族の分を削って、その日から居候を始めた遠い親戚にも平等に分けてあげたいと考える人は、一体どのくらいいるでしょうか。
――その裏にはおばさんなりに、家族を守るための必死さが隠れていた可能性が高いです。
そう考えると、おばさんは根っから冷たくてひどい人間ということではなく、彼女もまた戦争の被害者だといえるでしょう。
関連記事
観る人の心を揺さぶる『火垂るの墓』。その伝えたいことと、時代を超えて響くメッセージを考察します。
関連記事:火垂るの墓│伝えたいことは?実話や「ジブリじゃない」と言われる理由
おばさんは後悔した?正論?おばさん目線で考察まとめ【火垂るの墓】
今回はジブリ映画『火垂るの墓』のおばさんの後悔の有無などについてみていきました。
- おばさんは後悔した?:さほど後悔していないと思われる。
- おばさんは正論?:一理ある。
- おばさん目線でいうと?:自分たちが正しい、清太には助け合いの精神がない。
- 清太目線でいうと?:自分たちが正しい、おばさんは食事に贔屓があり冷たい。
- おばさんや娘はひどい?:ひどいし冷たい印象を受けるが、彼女もまた戦争に追い詰められた被害者
おばさんの行動や心理をどう受け止めるかは、視聴者それぞれの価値観によって変わります。
おばさんやその娘が冷たい態度をとっていることで、戦争によって引き起こされる二次被害について考えさせられます。
ご参考になりましたら幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。